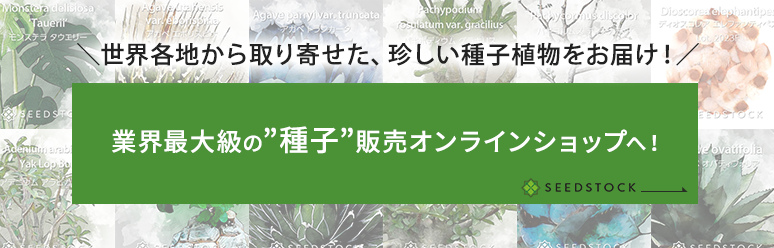-1.jpg)
多肉&観葉植物が好きで、約400鉢育てています。
さまざまな失敗をし、植物を枯らしたことは数知れず…。
失敗を通じて得た経験値をブログ(緑の日記)や執筆記事で情報発信し、植物好きをひとりでも増やしたい!
個性が光る‟一点物”
観葉植物や多肉植物などの葉に、白や黄などの模様が入った「斑入り(ふいり)」の植物。
他に類を見ない特徴から、斑が入った植物ばかりを集める“斑入りコレクター”も少なくありません。
また斑が入っていないものの、イカツイ姿をした‟ネームド”と呼ばれるアガベが、ここ最近高い人気を集めています。
ただし、斑入りの植物やネームドアガベのタネ(種子)は、一般的に流通することがありません。
その理由は斑入りの植物や、ネームドアガベから採れたタネをまいても、親と同様の特徴があらわれないためです。
本記事では斑入りの植物や、ネームドアガベのタネが流通しない理由について深掘りします。

斑入り品種や、ネームドアガベのタネが流通しない理由
斑入り品種
葉の一部を、白や黄色などに色づけた植物のことを「斑入り品種」と呼びます。
斑入りといっても、模様の入り方にはさまざまなタイプがあります。
たとえば、葉の縁の部分に斑が入る「覆輪斑(ふくりんふ)」、中央に入る「中斑(ちゅうふ)」、縞模様に色づく「縞斑(しまふ)」など。
ネームドアガベ
ワイルドな鋸歯を付けたり、短くて幅広の葉を展開したりする特徴的なアガベを、“ネームド(株)”または“ネームドアガベ”と呼びます。
ネームドアガベ(例)
- 白鯨(Agave titanota ‘White Whale’)
- レッドキャットウィーズル(Agave titanota’Red Catweazle’)
- ブラックアンドブルー(Agave titanota ‘Black & Blue’ )
特に最近は、多くのネームドアガベが誕生し、アガベ市場を賑わせています。
斑入りなどの特徴は、タネでは受け継がれない
一般的に、斑入りの植物やネームドアガベのタネは流通していません。
その理由は、葉を色付ける模様や株ごとの個性はタネでは受け継がれない、もしくは非常に不安定だからです。
花を咲かせタネを実らせる株と、タネから発芽する株は、親子の関係に当たります。
親子は似た特徴を持っていますが、全く同じわけではありません。
斑入り品種は、遺伝子の突然変異などによって生まれる
植物の葉を染める斑は、遺伝子の突然変異によって生まれることがほとんど。
園芸店に足を運べば、斑入り品種が多く並んでいるのは、人によって意図的に増やされたからです。
タネから発芽した植物に、斑の特徴があらわれる確率は低いです。
もし斑入りの植物が誕生したとしても、斑に染まる面積の分だけ葉緑体が少なく、成長速度が遅い品種が多いため、他の植物との生存競争に勝つのは難しいでしょう。
またネームドアガベのように、ワイドな葉に鋭い鋸歯を付ける特徴は、多くの株に見られるものではありません。

両親の遺伝子が組み合わされて子に伝わる
植物がタネを作る「有性生殖」という方法では、両親の遺伝子が組み合わされて子に伝わります。
タネを作る過程で、この「斑入り」や「株ごとの個性」はうまく伝わらないのが一般的です。
ちなみに、斑入りの植物から斑が抜けて、元々の植物の特徴があらわれることを「先祖返り」と言います。
植物の個性は、タネから育てる方法では受け継がれない
植物の斑は「キメラ」と呼ばれる特殊な状態
植物の斑は、「キメラ」と呼ばれる特殊な状態になっています。
キメラとは、「緑色の葉を作る組織」と「白や黄の模様を作る組織」の2種類の細胞が組み合わさり、一つの植物を作っている状態のことです。
「キメラ」が起こる原因は突然変異によるもの
キメラが起こる原因は、葉などに生じた「突然変異」です。
キメラの遺伝子は不安定なため、斑入り品種の遺伝子が組み合わさる過程で、先祖返りをしてしまう傾向があります。
アガベの鋸歯や葉の形状などは、株ごとの個性
アガベの鋸歯や葉の形状などは、それぞれの株が持つ個性です。
ネームドアガベから採取したタネから育った株の姿は、千差万別。
たとえ兄弟株でも、見た目が大きく異なることは、決して珍しいことではありません。
また、タネから育った「実生株(みしょうかぶ)」が、親株と全く同じ特徴を持つことはありません。
斑入りの植物から採れたタネが成長しても、斑の特徴はあらわれにくい
交配してタネができても、そのタネから育つ株は、斑の特徴を持たない「全部緑色」の葉に戻ってしまうことが多いです。
たとえるなら、斑入り植物の「白い部分」は“コピー機で印刷できない模様”のようなもの。
タネという設計図を作っても、その特殊な模様までは再現されないのです。
たとえ運良く斑が入ったとしても、親株とは異なる模様を付ける可能性もあります。
タネから育てる方法では、品種の特徴を担保できない
植物をタネから増やす方法では、安定して同じ特徴を再現できないため、斑入り品種やネームドアガベのタネが流通することはありません。
タネが流通している品種、流通していない品種
以下ではアガベの中で、タネが流通している品種と、流通していない品種の例を挙げます。
タネが流通している品種
- アガベ・オテロイ(Agave oteroi)
- アガベ・ポタトラム(Agave potatorum)
- アガベ・チタノタブルー(Agave americana)
タネが流通していない品種
- アガベ・イシスメンシス・ラムランナー(Agave · isthmensis; ‘Rum Runner’)
- アガベ・チタノタ(オテロイ)・白鯨(Agave Titanota “White Whale)
- アガベ・ポタトラム・吉祥冠錦(Agave potatorum ‘Kissho Kan’ variegata)
タネが流通していない品種の方が、増やしにくい分、希少価値が高い傾向があります。
斑入り品種やネームドアガベを増やす方法
斑入り品種やネームドアガベも、以下の方法で増やすことができます。
- 挿し木(さしき):茎や葉をカットし、土に挿す方法
- 株分け(かぶわけ):株元から出た子株を、根から分けて増やす方法
- 葉挿し(はざし):一枚の葉を土に挿し、葉の根元から新しい根(芽)を出させる方法
- メリクロン:組織を培養して増やす方法
上記の方法で増やされた植物は、親株と同じ遺伝子を持っているため、斑や鋸歯など、親株の特徴的な個性を引き継ぐことができます。
市場に出回っている斑入り品種やネームドアガベは、上記の方法で特徴的な株を増殖させたものです。
斑入り品種やネームドアガベが「一点物」でありながら、多くの株数が流通しているのは、このクローン増殖によるものです。
上記の理由から、斑入り品種やネームドアガベは、タネではなく株として流通しているのです。

実生の魅力
親株の特徴を完全に受け継げない実生ですが、タネから育てることにも魅力があります。
実生株は、一つひとつに違った個性があらわれるため、同じ株が二つと存在しません。
斑入りやネームド株のように“完成された見た目”を楽しむのもよいですが、実生は“未知の将来”を想像する楽しみがあります。
タネから育て、どんな姿に育つかを見守る過程そのものも、園芸の楽しみ方の一つです。
まとめ
「斑入りコレクター」を惹きつける斑入り品種や、ワイルドな姿が魅力的なネームドアガベ。
タネが流通せず、挿し木や株分けといった方法でしか増やせないのは、タネまきという手法では親株の特徴が受け継がれないから。
これは、斑入りの植物が「キメラ」という特殊な状態であることが原因です。
斑入り品種などは、増やしにくいがゆえに流通量が限られ、高い希少価値を生んでいます。
ある程度の大きさまで成長した、個性的な株を入手するのも園芸の一つの楽しみ方と言えるでしょう。