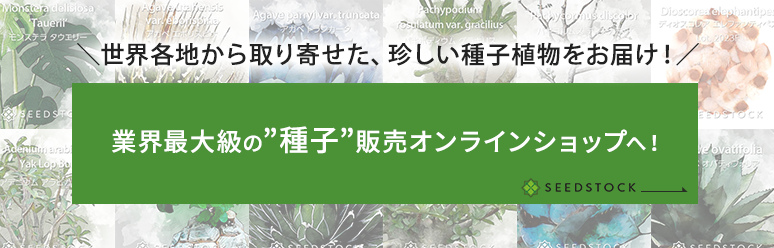観葉植物はお部屋を彩り、癒しを与えてくれる存在ですが、ペットを飼っていると「誤飲してしまわないか、毒性があるのでは?」と心配になります。
実際に、ペットにとって有害な植物も存在するため、安全性を考えながら選ぶことが大切です。
この記事では、ペットに安全な観葉植物の種類や、注意すべき植物、育てる際のポイントを詳しくご紹介します。
適切な種類を選び、育て方に工夫をすれば、ペットと観葉植物の両方を安心して共存させられます。
ペットと暮らしながら緑のある生活を楽しみたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
ペットを飼っていても観葉植物を育てることは可能!
ペットを飼っているからといって、観葉植物を諦める必要はありません。
犬や猫が植物をかじったり、誤って食べてしまったりすることがありますが、適切な種類を選び、安全な環境を整えれば、ペットと観葉植物の両方と一緒に生活できます。
ペットに無害な植物を選ぶことはもちろん、誤飲やいたずらを防ぐための工夫も大切です。
ペットと観葉植物を一緒に楽しむための、基本的な考え方やポイントを理解しておきましょう。
ペットに安全な観葉植物の種類

- パキラ
- ガジュマル
- テーブルヤシ
- ポトス
- エバーフレッシュ
ペットを飼っていても安心して育てられる観葉植物は数多くあります。
パキラは丈夫で育てやすく、ペットにも無害な観葉植物の一つです。乾燥や日陰にも比較的強いため、室内でも管理しやすいのが特徴があります。
ユニークな樹形が魅力のガジュマルは、ペットがいても育てやすい植物です。耐陰性があり、初心者でも比較的簡単に育てられます。
ヤシ科の植物の中でも、テーブルヤシはペットに対して安全です。成長が遅く手入れがしやすいので、室内で長く楽しめます。
ポトスは育てやすいことで人気の観葉植物ですが、品種によってはペットに有害なものもあります。
ポトスの中でも「マーブルクイーン」や「ゴールデンポトス」などの品種は毒性があるため、飼い主は注意が必要です。
アレカヤシは空気をきれいにする効果があり、ペットにとっても安全な植物の一つです。日当たりの良い場所を好みますが、室内でも元気に育ちます。
同じ植物でも品種によって毒性が異なります。観葉植物を選ぶ際には、必ず安全性を確認し、ペットが誤って口にしないように、適切な場所に配置することが大切です。
ペットの種類によっても毒性があるかないかが変わってくるので、飼っているペットに対して毒性がないか確認しましょう。
ペットを飼っている場合注意すべき観葉植物の種類

ペットにとって有害な成分を含む観葉植物は数多くあります。
ペットにとって危ない植物は、誤って口にすると中毒症状を引き起こす可能性があるため、ペットのいる家庭では注意が必要です。
ペットが植物を噛んでしまわないように手の届かない場所に置く、またはペットに安全な植物を選ぶことが重要です。
もしペットが誤食した場合は、症状に応じて速やかに動物病院を受診しましょう。
モンステラ
モンステラは大きな葉に特徴的な切れ込みが入る観葉植物で、耐陰性があり初心者でも育てやすい植物です。
モンステラの葉や茎にはシュウ酸カルシウムが含まれており、ペットが噛むと強い刺激を与えます。
もしモンステラを食べてしまった場合、口内や舌の腫れやよだれの増加、嘔吐、嚥下困難といった症状が現れます。
ドラセナ
ドラセナは細長い葉が特徴的で、観葉植物として人気です。耐陰性があり育てやすく、種類によって赤や黄色の縁取りがある品種もあります。
犬や猫が食べてしまうと、葉や茎に含まれるサポニンが消化器官に影響を与え中毒を起こし、嘔吐や食欲不振、うつ状態、ふらつきといった症状が現れます。
猫の場合は嘔吐に血がまじることもあるため、特に注意が必要です。
ユリ科の植物
ユリ科にはスパティフィラム、チューリップ、ヒヤシンスなど多くの品種が含まれます。
ユリやスイセンは猫にとって危険度の高い観葉植物です。
花・葉・茎・球根のすべての部分に有害な毒性があり、腎臓に深刻なダメージを与えます。
猫が食べてしまうと嘔吐や食欲不振、うつ状態、腎不全などの症状が現れます。
腎不全は摂取後24時間以内に発症しますが、放置すると命に関わる重大な影響を及ぼすので、すぐに獣医師の診察を受けましょう。
サトイモ科の植物
サトイモ科の植物には、アグラオネマ、フィロデンドロンなどの植物が含まれ、葉が美しい植物として人気があります。
葉や茎にシュウ酸カルシウムが含まれており、口や消化器官に強い刺激を与える毒性があります。
食べてしまうと口の腫れや炎症がおこり、よだれがひどくなったり、嘔吐したりする症状が出るので注意が必要です。
ヘデラ
ヘデラはつる性の植物で、壁やフェンスを覆うように育つため、室内のインテリアグリーンとして人気があります。
ヘデラの葉や茎にはサポニンやポリフェノール類が含まれるため、ペットが口にすると中毒を引き起こします。
口にするとよだれがたくさん出るだけでなく、嘔吐や下痢といった症状を引き起こすので注意が必要です。
飲み込まなくても、皮膚に触れるだけでも刺激を受けて皮膚炎になる恐れがあります。
ポインセチア
ポインセチアはクリスマスシーズンに人気の植物で、赤やピンクの鮮やかな葉が特徴です。茎や葉から出る白い樹液に毒性があり、ペットの皮膚や消化器官を刺激します。
目や口の粘膜への刺激が強く、皮膚に付くとかぶれや炎症を引き起こし、誤って口にした場合は嘔吐や下痢などの症状が現れます。
ペットを飼っている家で観葉植物を育てるためのポイント

ペットと観葉植物を共存させるためには、植物の選び方や配置、育成環境の工夫が重要です。
有害な植物を避け、安全な種類を選ぶだけでなく、誤飲を防ぐために配置を検討することが大切です。
農薬や肥料などの使用にも注意し、ペットが口にしても害のないものを選びましょう。
安全性を確認してから植物を選ぶ
観葉植物を購入する際は、ペットにとって安全かどうかを必ず確認しましょう。
ペットに無害な植物でも、品種によっては毒性がある場合があるため、事前に詳しく調べることが大切です。
ポトスの一部の品種は無害ですが、一般的なポトスはペットに有害です。同じ種類でも成分が異なることがあるため、植物の学名や正式な品種名を確認しましょう。
購入後もしばらくペットの様子を観察し、興味を持ちすぎていないか注意する必要があります。
配置場所など育成環境を工夫する
観葉植物の配置を工夫することで、ペットが誤って食べたり、倒したりするリスクを減らすことが可能です。
基本的な対策としては、ペットが届かない範囲に置くのが有効ですが、猫は高い場所にも登るためただ棚の上に置くだけでは不十分な場合もあります。
植物の周りにフェンスを設置すれば、物理的に植物に近付くのを防げます。大型の観葉植物は倒れる危険があるため、転倒防止をしてより安全性を高めましょう。
ペットが苦手とする柑橘系の匂いやミントなどの特定のハーブを使うのも有効です。
植物の周りにレモングラスやローズマリーを置く方法も、ペットが近寄りにくくする効果があります。
農薬や殺虫剤、肥料に注意する
観葉植物を健康に育てるためには、肥料や殺虫剤を使うことがありますが、多くの農薬や肥料にはペットにとって有害な成分が含まれているため、慎重に選ぶ必要があります。
一般的な殺虫剤は、ペットにとって危険な成分が含まれている場合が多いです。
ピレスロイド系や有機リン系、ネオニコチノイド系の薬品が入っていないか確認しましょう。
観葉植物用の肥料にも、化学成分が含まれているものが多いため、ペットが誤飲すると中毒を起こします。
特に、液体肥料はこぼれやすいため注意が必要です。
固形肥料は土の中にしっかり埋め込めば比較的安全ですが、ペットが観葉植物の土を掘ったり食べたりすることもあります。
もしペットが誤飲したら状況に応じて動物病院の受診を
ペットが観葉植物を誤って食べてしまった場合は、まず状況を確認しましょう。
ユリ、ポインセチア、サトイモ科の植物などの毒性の強い植物を口にした場合は、すぐに動物病院を受診してください。
特にユリは猫にとって非常に危険で、少量でも腎不全を引き起こす可能性があります。
無毒な植物を少量かじった程度であれば、嘔吐や下痢などの症状が出たり、元気がなくなったりしていないか観察してください。
異常がなければ様子を見るだけで問題ありません。大量に食べてしまった場合や、食欲不振などの症状が見られた場合は、念のため動物病院に相談するのがおすすめです。
植物の名前や食べた量を記録しておくと、適切な対応がしやすくなります。
まとめ
ペットと観葉植物の両方と一緒に生活することは、十分に可能です。
安全な植物を選んで配置を工夫し、農薬や肥料にも注意すれば、ペットの健康を守りながら緑のある暮らしを楽しめます。
もし誤飲しても、適切に対処すれば大きな問題になることは少ないため、必要以上に不安にならず、まずは安全対策を徹底しましょう。
ペットとの暮らしに癒しのグリーンを取り入れて、より快適な空間を作りましょう。